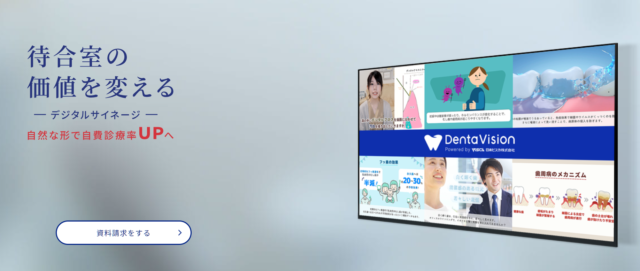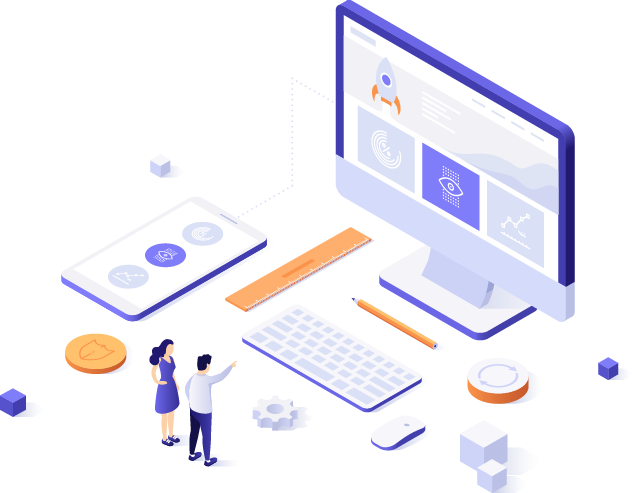(はじめに)
厚生労働省「医療施設調査・病院報告の概要」によれば、2019年の歯科診療所数は6万8,500軒あります。コンビニ店舗数の5万5,620軒を上回っていることからも、歯科医院は差別化しにくく、患者さんが歯科医院を選ぶ時代であることがわかるかと思います。
ホームページ開設する歯科医院は8割以上に増えましたが、上手に運営できているところはごく一部だといえるでしょう。歯科医師の先生や、歯科衛生士さんからブログで上手に情報発信することができれば、自院と患者さんとのコミュニケーションとなり差別化が図りやすくなります。この記事では、歯科医院がブログを書いた方がいい理由をご紹介します。実際に、集患に成功した事例も掲載しているため、参考にしてみてください。
1.SEO対策でアクセス数のアップが狙える
歯科医院でブログ運営をすれば、SEO対策ができてアクセス数のアップが期待できます。ただし、やみくもに記事数を増やしたり、医院や治療と関係のない日常ブログのような記事ではSEO対策としては意味がないため、何をテーマにするかきちんと設定することが必要です。そのためにブログ運営前に、自社の強みやアピールポイントを明確にしておきましょう。
ブログ記事1つにつき1つの明確なテーマを設定し、タイトルには、テーマの「キーワード」を入れたわかりやすいタイトルを設定しましょう。ブログの文字数は1,000文字程度はあったほうがよく、構成をわかりやすくするために「小見出しを入れる」ことも重要です。テーマのイメージを喚起させる写真も入れて、視覚的にもアピールしましょう。また記事の最後には執筆した歯科医師の写真やプロフィールをいれることで記事に専門性を持たせたり、読み手に親近感を与える効果もあります。
成功事例
東京のある歯科医院では、ブログ運営するにあたって、どのようなコンテンツが欲しいかを患者さんにリサーチしたそうです。患者さんからよくある質問など、実際に求められている情報を提供し続けた結果、検索でヒットするようになり、アクセス数が大幅にアップ。患者の悩みに応えてくれる歯科医院として集患に成功しています。
2.オリジナルコンテンツで差別化が図れる
患者さんから選ばれる歯科医院になるためには、差別化は必要不可欠です。ブログでオリジナルコンテンツを配信するだけで、他院との差別化は図りやすくなります。独自の取り組みなど差別化のポイントを見つけて、柔軟にコンテンツ配信していけることがブログの魅力です。
成功事例
競合が多い東京駅にある矯正歯科専門の歯科医院は、他社と差別化を図るために、素人が見てもわかるかみ合わせのBefore・Afterの写真をデータとともに掲載しました。他院では治療後の歯並びがキレイな写真のみが掲載されていたため、Before写真を掲載することで差別化を図ることに成功。
歯科矯正の実績を豊富に持つ歯科医院として注目を浴びることができ、Web予約数が10倍にアップしました。
3.専門的な情報提供で信頼を獲得できる
各症状の治療法など専門情報を提供することで、患者さんから信頼を獲得することができます。一般的に、良い情報も悪い情報も含めて多くの情報を提示したほうが客観性が高く感じられ、信頼も得やすくなる心理効果があります。そのため、治療方針や治療技術などの情報提供は積極的にしましょう。治療のリスクやデメリットもある程度書いておくことは医療広告ガイドライン対策にとどまらず、患者さんに誠実な印象を与え、治療後のクレーム防止にもつながります。
成功事例
横浜市にある歯科医院は、ブログ内で治療技術の動画を配信。これまで、治療技術を写真や文字でしか伝えることができませんでしたが、YouTubeの登場で手軽に動画配信が可能となりました。動画配信を活用して、どのような治療方法なのかわかりやすく解説。
このようなブログ運営で、関東以外からも患者さんが訪問してくるほどの人気歯科医院に成長しました。
まとめ
歯科医院がブログ運営をすると、3つのメリットが得られます。
- SEO対策でアクセス数アップが狙える
- オリジナルコンテンツで差別化が図れる
- 専門的な情報提供で信頼を獲得できる
この記事では、実際にブログ運営で集患に成功した事例もご紹介しました。ぜひ、ブログ運営の参考にしてみてください。また、ブログ運営が自身で行えない場合は、専門業者に依頼する方法も1つです。日本ビスカではSEO対策の一環としてブログ(コラム)運営を行っています。人気のあるテーマやキーワードに沿って、医院独自の取り組みや季節に合った話題を盛り込んだオリジナルの記事作成もご好評いただいています。ご興味を持った方はお気軽にご相談ください。

成果報酬型SEOサービス
インターネット経由の集患を増やせるかどうかはSEO対策をしっかりできているかといっても過言ではありません。
ビスカでは、成果がでなければ一切費用を頂かない「成果報酬型」SEOサービスをご提供しています。