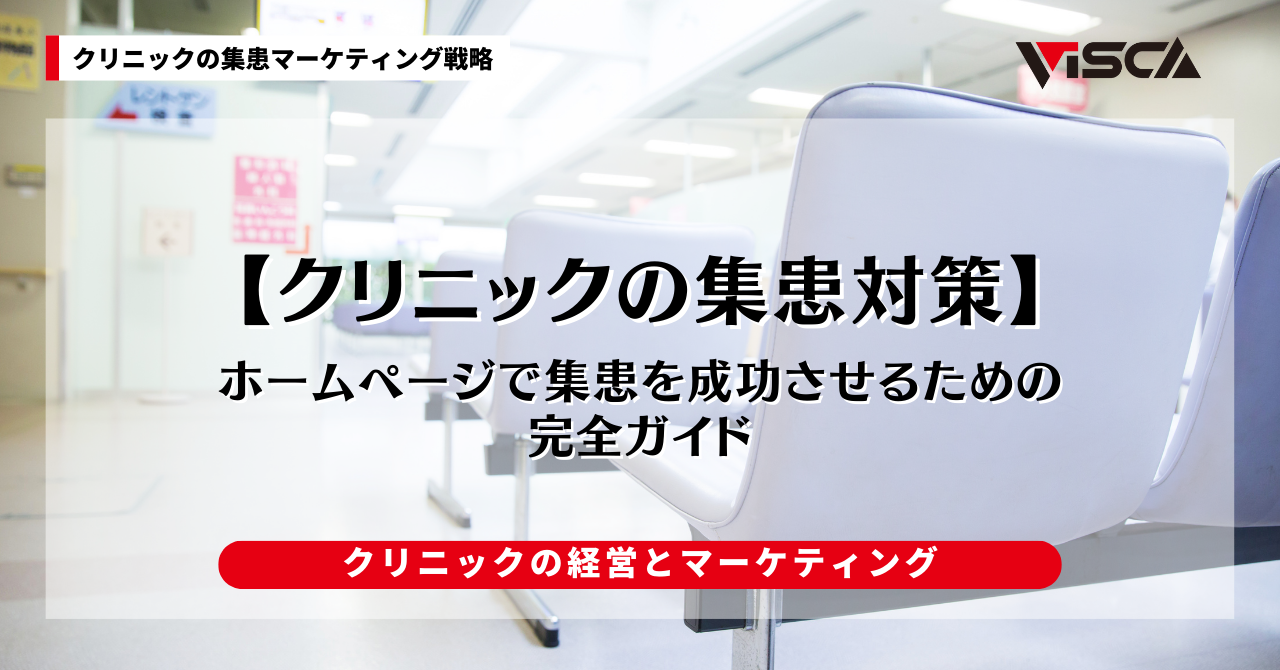医療機関の広告表現には、一般の商業広告と異なる厳しいルールが存在します。特に歯科や美容医療分野では、「今だけ割引」「モニター価格」といった表現を見かけることもありますが、こうした費用を強調する広告は原則として医療広告ガイドライン違反となります。本記事では、医療法とガイドラインの関係から、割引表示がNGとされる理由、具体的な違反事例、法的リスク、正しい費用表示の方法まで、厚生労働省などの公的情報をもとに徹底的に解説します。信頼される医療広告の実践に向けて、ぜひご一読ください。
医療広告ガイドラインとは?
医療広告ガイドラインは、医療機関が広告を行う際に守るべきルールを定めたものです。医療法に基づき、虚偽や誇大な表現、患者の誤認を招く表現を防ぐことを目的としています。まずはこのガイドラインがなぜ制定され、どのような媒体や情報が対象になるのかを理解することが、広告違反を防ぐ第一歩となります。
医療法との関係と法的背景
医療広告は、医療法第6条の5により「虚偽・誇大・比較優良広告」が禁止されています。厚生労働省が示すガイドラインでは、広告表現の基準がより具体的に明記されており、法的な背景が整備されています。
ガイドラインの目的:患者に客観的・正確な情報提供
ガイドラインは、患者が適切な医療を選べるよう「客観的かつ正確な情報提供」を目的としています。治療内容・リスク・費用・回数を正しく開示し、「扇情的な訴求」を排除することが求められています。
対象媒体:ホームページ、SNS、チラシ、動画など
すべての媒体で「患者を誘引する意図」がある情報は対象となります。特に、ホームページやSNS、動画やチラシなど、直接的な広告目的で使用される媒体は厳しくチェックされます。また、これらの広告媒体に誘導するQRコードも広告とみなされる場合があります。
なぜ「割引表示」はNGなのか?
「自由診療が安くなる」という表現は一見魅力的に思えますが、医療広告では基本的に禁止されています。なぜ割引表示がNGなのか。その背景には、医療の品位保持や患者保護といった重要な視点があります。このセクションでは、費用強調表現が持つリスクや、特に問題となるケースについて詳しく解説します。
「費用を強調した広告」は品位を損ねる表現として禁止
ガイドラインでは「費用訴求」は“品位を損なう”表現とされ、費用のみを強調する広告は全面的に禁止されています。
患者を不当に誘引するリスクと消費者保護の視点
割引訴求は”今すぐ利用したい”という心理を引き出しやすく、医療が消費財化する恐れがあります。ガイドラインは消費者保護の観点から、こうした表現を厳しく制限しています。
特に歯科・美容医療に多い割引訴求の実態
美容・歯科分野では「◯%OFF」などの割引表示が横行していますが、厚労省が掲示するガイドラインでは、割引表現=不当な誘引と見なされ、規制の対象になっています。
割引表示やキャンペーン例の違反事例
実際に違反とされた割引広告にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、「今だけ〇%OFF」や「モニター価格」といった表現を例に、どのような広告が医療広告ガイドラインに抵触するのかを具体的に紹介します。違反リスクを避けるためにも、NG表現の具体例を知ることは非常に重要です。
「今だけ◯%OFF」「モニター価格」表示のNG具体例
「今だけ50%OFF」「モニター募集価格」などの割引訴求は、誘引性の強い典型的な違反表現であり、使用すると行政指導の対象になります。
「通常価格→割引後価格」のような強調も禁止
二重価格表示(例:¥100,000→¥80,000)や装飾での強調も規制対象です。利益の強調はすべてNGとされています。
検討可能な費用表記とは?
治療費は客観的かつ正確に表示可能です。
・セラミッククラウン:120,000円(税込・自由診療)
といった形で、淡々と記載しましょう。
遵守すべき費用表示の方法と表現のルール
割引表示が禁止されているとはいえ、すべての費用表記がNGなわけではありません。医療広告では、患者が治療前に費用の目安を知ることができるよう、一定の条件下での表示が認められています。このセクションでは、自由診療・保険診療それぞれの費用表示のルールと、誤認を防ぐための注意点を整理します。
自由診療・保険診療の違いと表示ルール
自由診療は「自由診療」である旨の記載が必須です。保険診療も必要に応じて費用記載は可能ですが、表現は控えめにしなければなりません。
費用表示は客観的・正確に、誤認を与えない形で
税込・税抜・回数など、詳細を正確に記載し、強調表現は避けます。「標準的な費用」を書き、異なる場合は理由を添えると良いでしょう。
患者さんへの事前説明と同意(インフォームドコンセント)の重要性
広告表現だけでなく、実際の診療でも説明責任を果たすことが必要です。広告内容と診療内容の整合性を持たせることが、患者さんとの信頼を築きます。
違反リスクと行政対応の事例
もしガイドラインに違反した場合、医療機関にはどのようなリスクがあるのでしょうか。ここでは、実際に発生した行政指導や刑事処分の事例を取り上げ、違反が経営・信頼に与える影響についても詳しく解説します。罰則の内容を知っておくことで、より適切なリスク管理が可能になります。
行政指導・是正命令から刑事処分まで
違反が発覚すると、行政指導や中止命令、改善命令が行われ、違反が改善されず悪質と判断された場合は、医療法第6条の5に基づき6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性もあります。
患者からの信頼低下や風評被害の可能性
違反広告はブランド価値の毀損につながり、SNSや口コミなどで拡散されれば、地域での評価に深刻な影響を与えます。
医療機関が安全・効果的な広告を行うために
ルールに則った広告でも、伝わらなければ意味がありません。このセクションでは、法令を守りながらも効果的に伝えるための工夫、広告制作時のチェック体制の整備、外部制作会社との連携方法など、医療機関として実践すべき具体策をご紹介します。
スタッフ研修とチェック体制の整備
スタッフ全員へガイドラインを周知し、広告作成前後のチェック体制を社内に整備することが不可欠です。
制作会社と連携した広告内容のレビュー体制
外部制作を依頼する場合でも、最終責任は医療機関にあるため、必ず内容を確認し、修正依頼をしましょう。
動画・デジタルサイネージ含むE‑A‑T型広告戦略の活用と注意点
動画やデジタルサイネージでは、専門性・経験・設備紹介などの情報提供型コンテンツが望ましいです。割引訴求を含む表現は使用しないよう徹底しましょう。
動画制作において気をつけるべき点
動画やデジタルサイネージは、今や医療機関のブランディングに欠かせないツールです。しかし、その訴求力の高さゆえに、ガイドライン違反に繋がる表現が入りやすい領域でもあります。このセクションでは、情報提供型動画の活用方法や、信頼性の高いコンテンツ作成のポイントをわかりやすくまとめています。
情報提供型動画はOK、割引訴求型はNG
院内紹介、ドクター紹介、施術の流れなど、教育的・啓発目的の動画は適切です。
一方、「◯万円OFF」などの割引を目的とする動画訴求は規制対象で、制作自体がNGです。
院内紹介や専門性を示す動画でE‑A‑Tを強化する方法
- 院長の専門経歴・認定などを紹介
- 実際の施術コメント
- 患者への配慮や安全性の説明
これらを含む動画は、専門性と信頼性の訴求=E‑A‑Tを高める効果があると言われています。
まとめ:患者に信頼される表現で集患するには?
- 割引表示は禁止。費用は客観的かつ淡々と記載
- 自由診療は「自由診療」の明記が必須
- 治療内容・リスク・回数も明記し、体験談・モニター広告は原則禁止(条件付きでOK)
- スタッフ教育と制作会社との体制整備を実施
- 動画やデジタルサイネージでもE‑A‑T重視の情報提供を
ガイドラインを遵守し、信頼される広告を行えば、地域で選ばれる医療機関に成長できます。
ご希望があれば、チェックリストやリライト例もご用意できますので、お気軽にご相談ください。

リスティング広告
短期的にホームページのアクセス数を増やしたい場合には、確実に検索結果上位に表示されるリスティング広告がお勧めです。
ビスカではGoogle広告の有資格者が、集患に繋がりやすい効率的な運用を行っております。
日本ビスカ株式会社について
日本ビスカ株式会社 は、医療機関向けのWebマーケティング支援を専門に行っています。
- ホームページ制作:3,500医院超の制作実績。患者さんに選ばれるデザインと機能性を両立させたホームページ制作を行っています。
- SEO/MEO対策:地域密着型の施策で競争力を強化、エリアで選ばれるクリニックとしてブランディングを支援します。
- 広告運用:効率的なリスティング広告やインスタグラム広告など、目的にあわせたWEB広告で費用対効果を最大化します。
資料請求・お問い合わせ
資料請求やお問い合わせは、こちらのフォームからどうぞ。専門スタッフが丁寧に対応いたします。
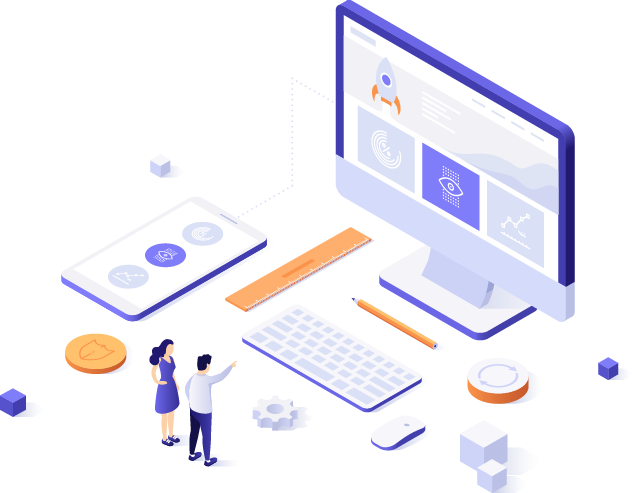
ホームページ制作サービス
ホームページは、クリニックの資産として育てていくことができるものです。まずホームページを開設することは、インターネットから集患するうえで欠かすことはできません。
ビスカでは、公開までのスケジュールやニーズ、ご予算に合わせて柔軟に対応できるホームページ制作プランを3つご用意しております。