今やホームページは、クリニック経営に欠かせない「第二の受付窓口」です。
患者さんはまずネットで医療機関を探し、診療内容や雰囲気、アクセス情報などを比較してから来院を決める時代。
診療内容や医師の人柄、診療時間やアクセスなど、患者さんが知りたい情報をしっかり掲載しておくことは、信頼と安心感の提供にもつながります。
この記事では、「クリニック ホームページ 作り方」というテーマのもと、ご開業の先生や院長、運営担当者が知っておくべき基本の構成、制作ステップ、SEO対策までを丁寧に解説します。
「どこから手をつけたらいいかわからない」という方も、このコラムを読めば、患者さんに選ばれるホームページの作り方がしっかり見えてくるはずです。
クリニックホームページの基本構成【最低限これだけは必要】
ホームページを作成する際、まず押さえておきたいのが基本構成です。
最低限必要なページは以下のとおりです。
- トップページ(クリニックの概要や強み)
トップページは、訪問者が最初に目にする入口です。
どのようなクリニックなのか、診療内容の概要、地域との関わり、設備の特長などを簡潔に紹介しましょう。
「初めての人が安心できる印象づけ」を意識し、予約ボタンや診療時間への動線も目立たせることがポイントです。
- 診療科目ページ(内科、皮膚科、歯科など)
患者さんが一番知りたいのは「自分の症状に対応してもらえるかどうか」です。
各診療科ごとに、対応する病気・症状、検査内容、治療方針などを具体的に記載することで、安心感と信頼性を高めることができます。
可能であれば、医師の専門分野や設備との連携についても触れると効果的です。
- 医師紹介ページ(院長あいさつ、経歴など)
医師の顔や経歴、考え方が見えることで、初診の不安が和らぎます。
「どんな先生が診てくれるのか」「どんな理念で診療しているのか」が伝わることで、共感や信頼につながります。
顔写真の掲載も強くおすすめします。人柄がわかる文章があると、より来院のハードルが下がります。
- アクセスページ
患者さんにとって最も実用的なページの一つです。
アクセス情報だけでなく地図や最寄り駅・バス停の案内、駐車場の有無も忘れずに掲載しましょう。
スマートフォンからでも見やすいよう、表形式やGoogleマップの埋め込みも有効です。
他にも重要な医院情報である休診日や診療時間、土日診療の有無などはサイト内のページに共通して掲載できるヘッダーやフッターに記載するのが良いでしょう。
- お知らせ・ブログ(最新情報の発信)
診療の休止情報や臨時対応などを迅速に伝えるための更新エリアです。
また、予防医療や季節の健康情報などを発信することで、信頼感や専門性のアピールにもつながります。
継続的な更新はSEOにも好影響を与えるため、定期的な運用をおすすめします。
これらの情報を整理してわかりやすく伝えることで、患者さんが安心して来院できるホームページになります。
クリニックホームページの作り方ステップ
クリニックのホームページを作ろうと思っても、「何から始めればいいのか分からない」と感じる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、初めてでも安心して取り組めるよう、ホームページ制作の基本的なステップを順番にご紹介します。
実際に制作会社に依頼する場合にも、自作する場合にも共通する流れですので、ぜひ参考にしてください。
目的とターゲットを明確にする
「新患を増やしたい」「予防医療を発信したい」「求人を出したい」など、目的によってサイトの構成や導線は変わります。
来院してほしいターゲット(高齢者、小児、働く世代など)を明確にすることで、デザインや文章も具体的に調整できます。
制作会社に依頼 or 自作?
医療専門のホームページ制作会社に依頼すれば、法令や医療広告ガイドラインに沿った適正な内容で制作してもらえます。
一方で、自作ツール(Wix、Jimdo、ペライチ、WordPressなど)を活用すれば費用を抑えて自院の色を出すことも可能です。
ドメインとサーバーを取得
ホームページの住所であるドメインは、「地域名+院名」がおすすめです(例:yoga-naika.com)。
信頼性やセキュリティの観点から、安定したレンタルサーバーを選ぶことも重要です。
原稿・写真素材を用意する
医師紹介、診療内容、アクセス情報、診療時間などの原稿は事前に用意しておくとスムーズです。
院内やスタッフの写真も、信頼感や安心感を与える大切な要素です。
公開後の対応
ホームページ公開後は、Googleビジネスプロフィールやマップ登録、検索エンジン向けの登録(サーチコンソール)を行い、患者さんに「見つけてもらえる仕組み」を整えます。
チラシやSNSと連動させるのも有効です。
SEOで患者さんに見つけてもらうために意識すべきこと
どれだけ魅力的なホームページでも、見つけてもらえなければ意味がありません。
SEO対策として最も基本かつ重要なのが「地域名+診療科名(例:世田谷区 内科)」のキーワードを意識したページ作りです。
見出し(h1・h2)や文章中に適度にキーワードを散りばめ、検索エンジンにわかりやすく構造化されたページを構成しましょう。
さらに、スマートフォンでの閲覧に対応したレスポンシブデザイン、ページ表示の速さ、定期的な情報更新(ブログ・お知らせ)もSEOには有効です。
よくある失敗とその対策
ホームページは作って終わりではなく、「作ったあと」の運用がとても重要です。
ここでは、クリニックサイトでありがちな失敗と、その対策について具体的にご紹介します。
情報が古いままになっている
診療日や担当医の情報、季節性のワクチン情報などが数年前のままになっていると、「このクリニックはきちんと運営されているのか?」と不安を抱かせてしまいます。
最低でも月に1回程度、お知らせ欄を更新することで「生きているサイト」として検索エンジンにも評価されやすくなります。
キャンセル情報や診療時間の変更だけでなく、季節の健康アドバイスなども投稿内容として有効です。
写真が暗く、院内の雰囲気が伝わらない
「せっかくおしゃれな内装にしているのに、ホームページの写真では伝わらない…」というケースはよくあります。
スマートフォンで撮影した写真は、光量や構図の面で限界があります。
プロのカメラマンに依頼し、院内・外観・スタッフの写真を丁寧に撮ってもらうことで、患者さんに安心感と信頼感を与える大きな要素となります。
診療時間や休診日の記載ミス
「実際の診療時間とホームページの記載が違っていた」というケースは、患者さんの不満やクレームにつながる最も重大なミスの一つです。
変更があった場合は即時反映を行い、常に最新の状態を保ちましょう。
また、Googleビジネスプロフィールや予約サイトなど外部サービスとの情報統一も忘れずに行うことで、信頼性の高いクリニックという印象を与えることができます。
ホームページ制作は一度作って終わりではなく、継続的に見直しと改善を重ねることが重要です。
医療広告ガイドラインに注意
医療機関のホームページは、「医療広告ガイドライン」の規制対象です。
たとえば、ビフォーアフター画像、体験談、誇大な表現(例:「絶対に治る」「痛くない治療」)などは掲載に注意が必要です。
制作会社に任せる場合も、自院がどのような情報を発信しているかを必ず確認し、適切な表現で構成されているかをチェックしましょう。
ホームページは捉え方によっては立派な広告の一部にもなり得るため、自由に表現して良い、というわけではありません。
ホームページは“集患ツール”以上の存在
ホームページは単なる宣伝ではなく、「誰に・どのような医療を届けたいか」を明確に伝えるメディアです。
紹介に頼らず、自院の魅力を正しく届けることで、新患の獲得だけでなく、採用活動や地域連携のハブとしても機能します。
患者さんが「ここに行ってみよう」と安心できるホームページを作ることが、地域医療の信頼構築につながります。
まとめ|信頼される医療の入口としてのホームページ
クリニックのホームページは、患者さんにとって最初に出会う「診療の顔」です。
丁寧に設計されたサイトは、集患効果だけでなく、地域社会との信頼関係づくりや、スタッフ採用、口コミにも影響を与えます。
どんなに忙しい日常の中でも、伝えたい想いがあるならば、それを形にするホームページはきっと力になってくれるはずです。
まずは基本を押さえ、信頼される医療の入口として、ホームページづくりを始めてみませんか?
日本ビスカ株式会社について
日本ビスカ株式会社 は、医療機関向けのWebマーケティング支援を専門に行っています。
- ホームページ制作:3,500医院超の制作実績。患者さんに選ばれるデザインと機能性を両立させたホームページ制作を行っています。
- SEO/MEO対策:地域密着型の施策で競争力を強化、エリアで選ばれるクリニックとしてブランディングを支援します。
- 広告運用:効率的なリスティング広告やインスタグラム広告など、目的にあわせたWEB広告で費用対効果を最大化します。
資料請求・お問い合わせ
資料請求やお問い合わせは、こちらのフォームからどうぞ。専門スタッフが丁寧に対応いたします。
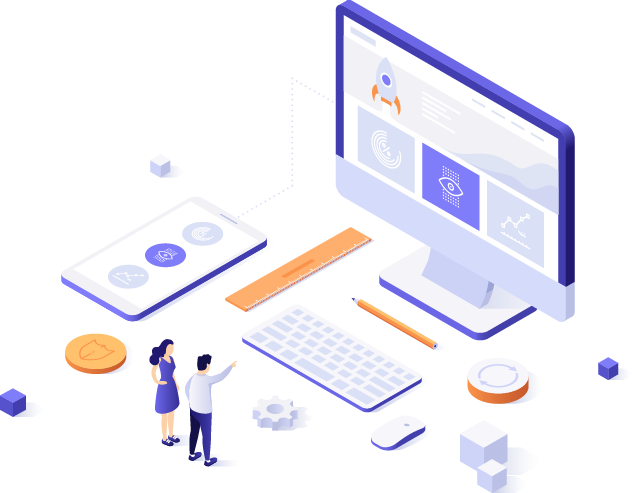
ホームページ制作サービス
ホームページは、クリニックの資産として育てていくことができるものです。まずホームページを開設することは、インターネットから集患するうえで欠かすことはできません。
ビスカでは、公開までのスケジュールやニーズ、ご予算に合わせて柔軟に対応できるホームページ制作プランを3つご用意しております。

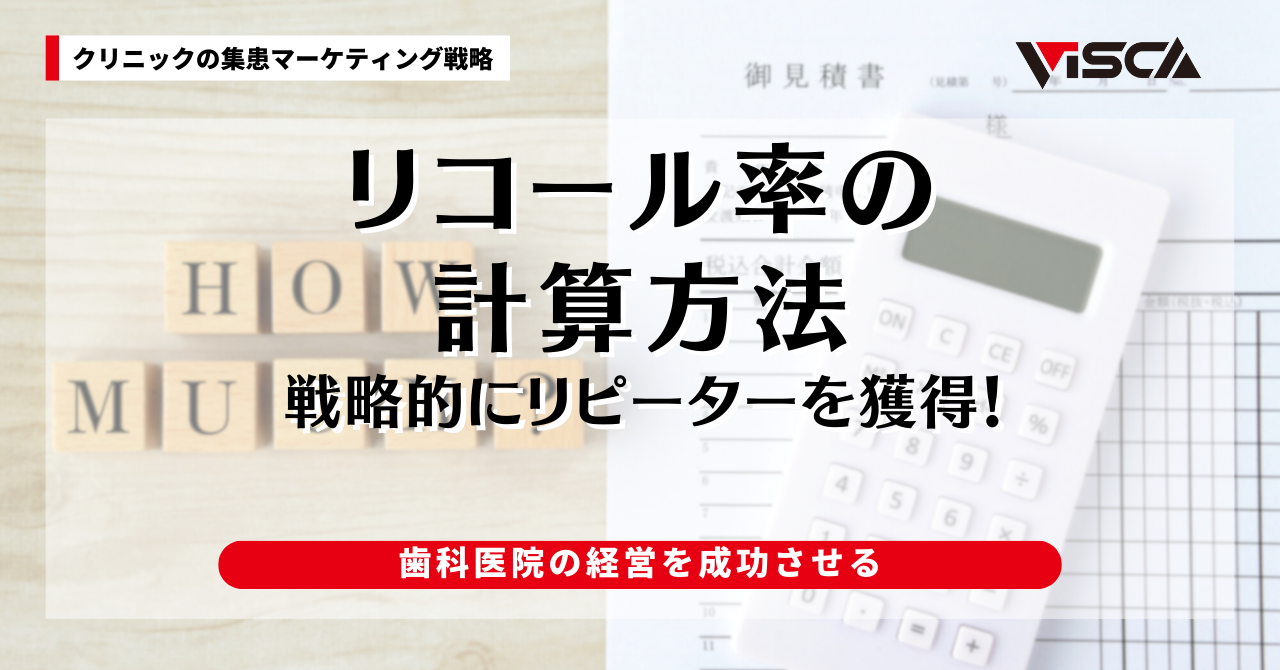



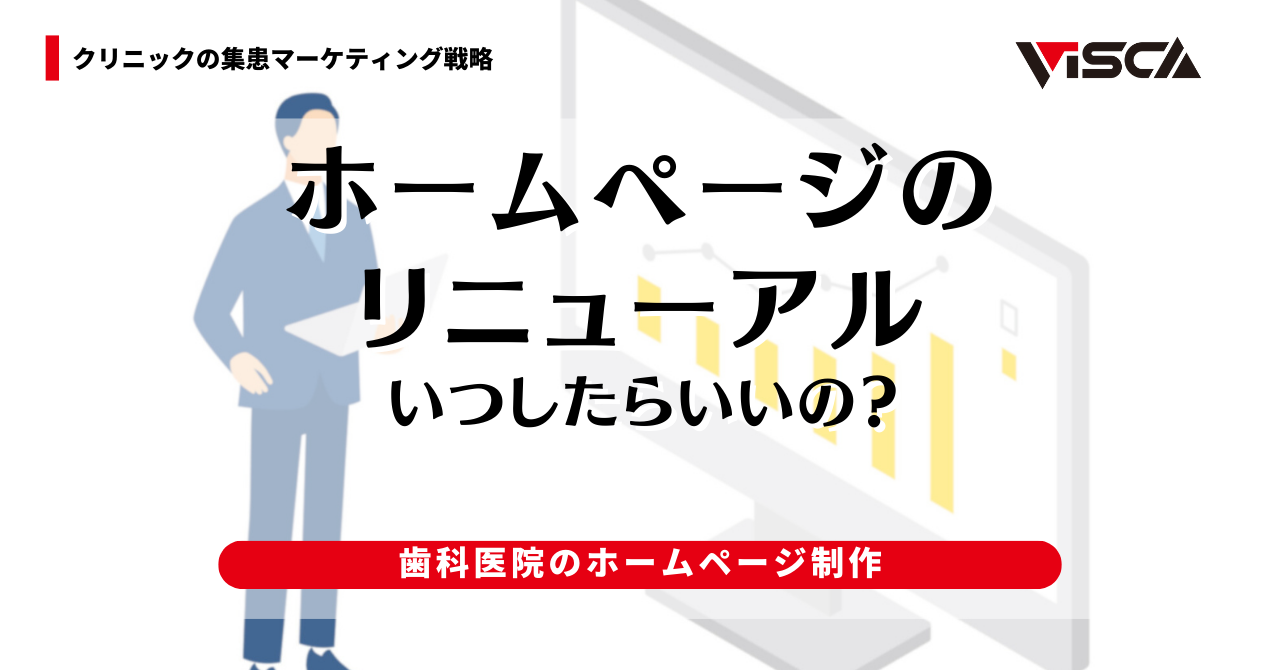



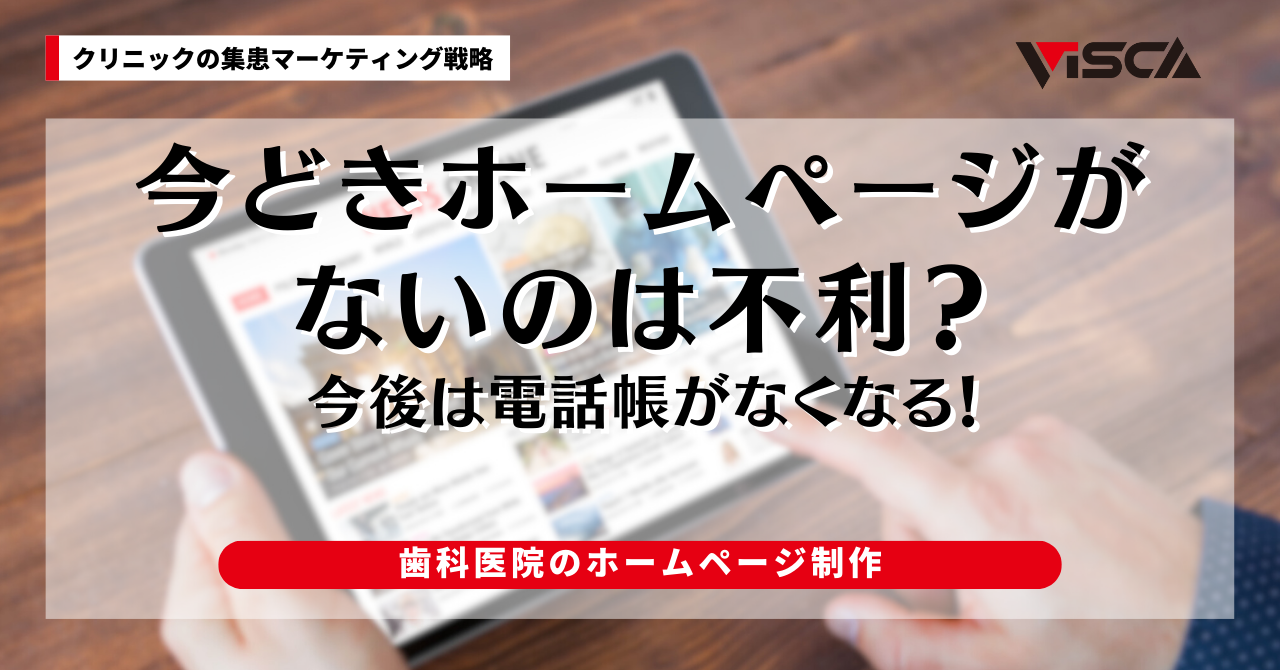

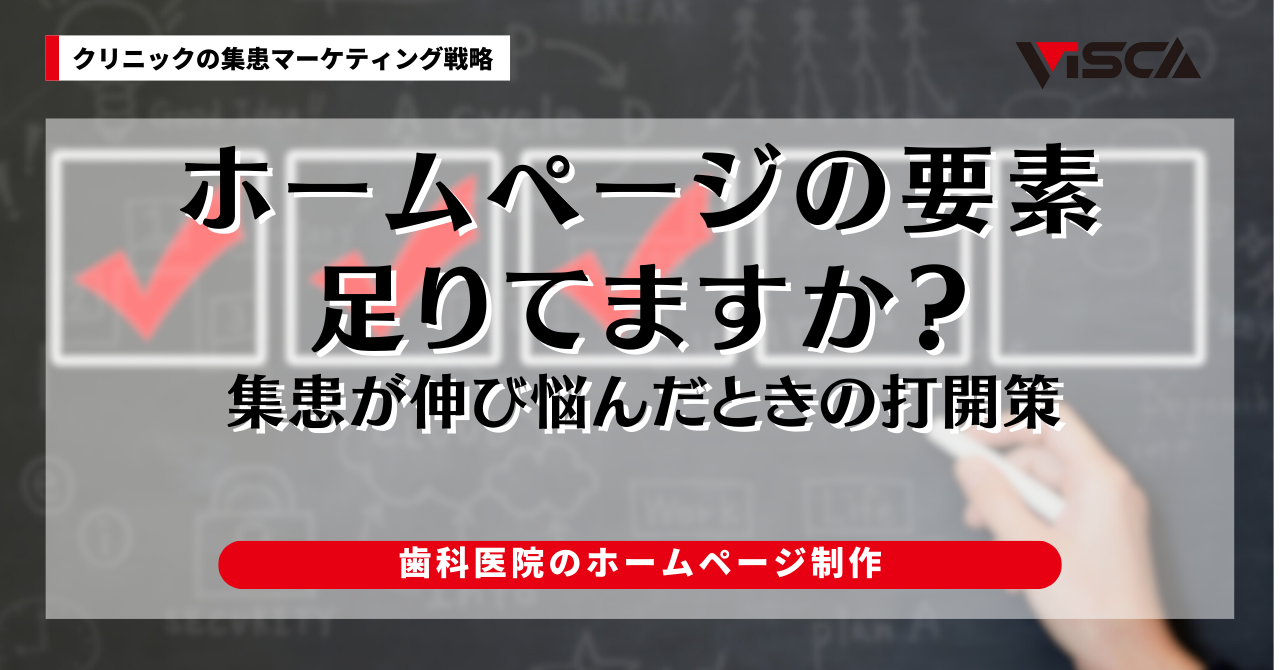






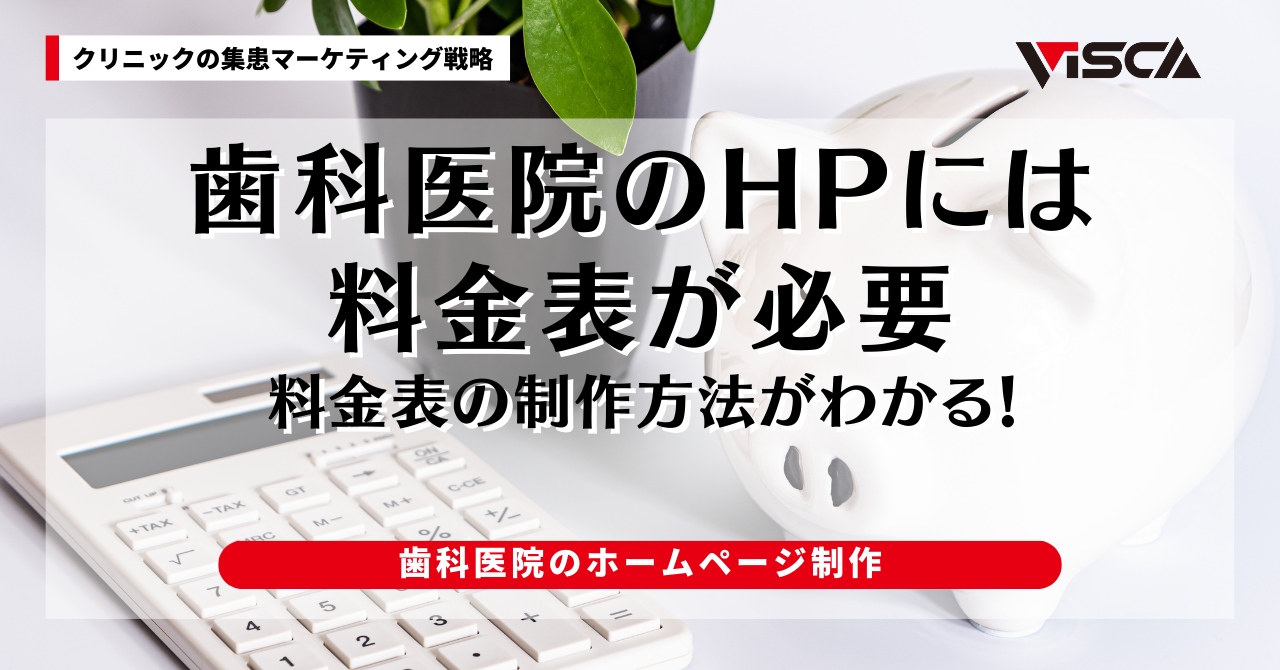




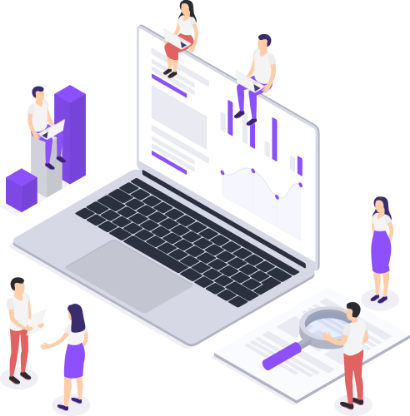
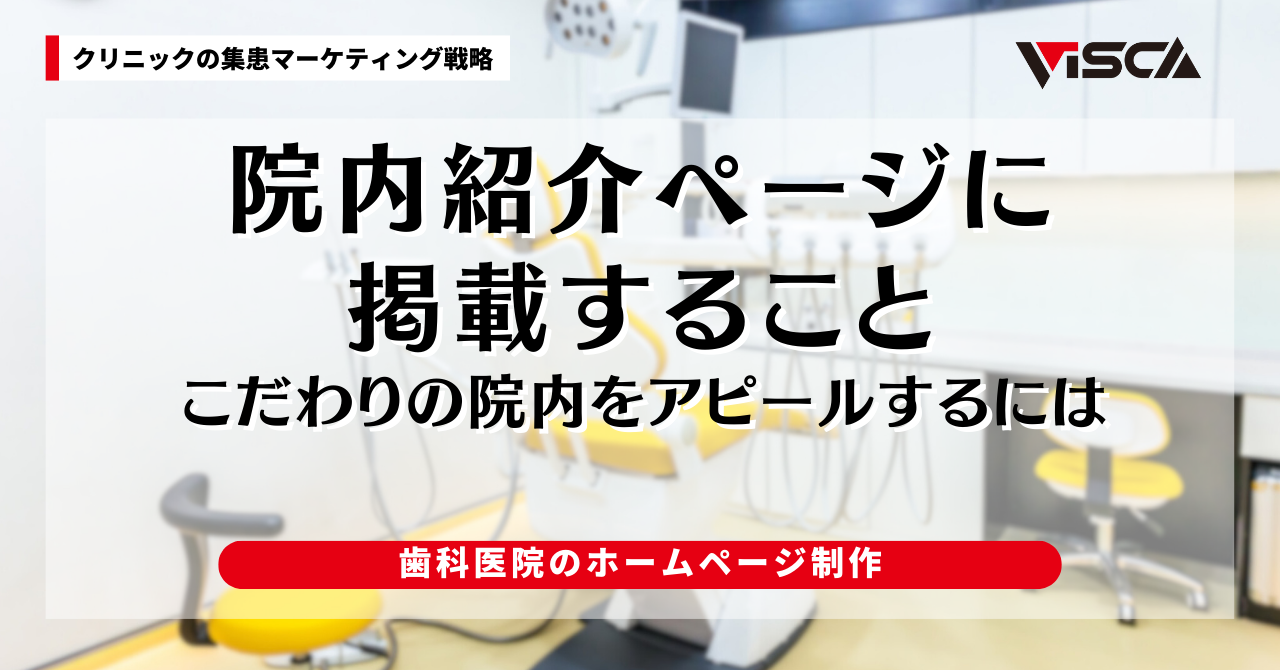







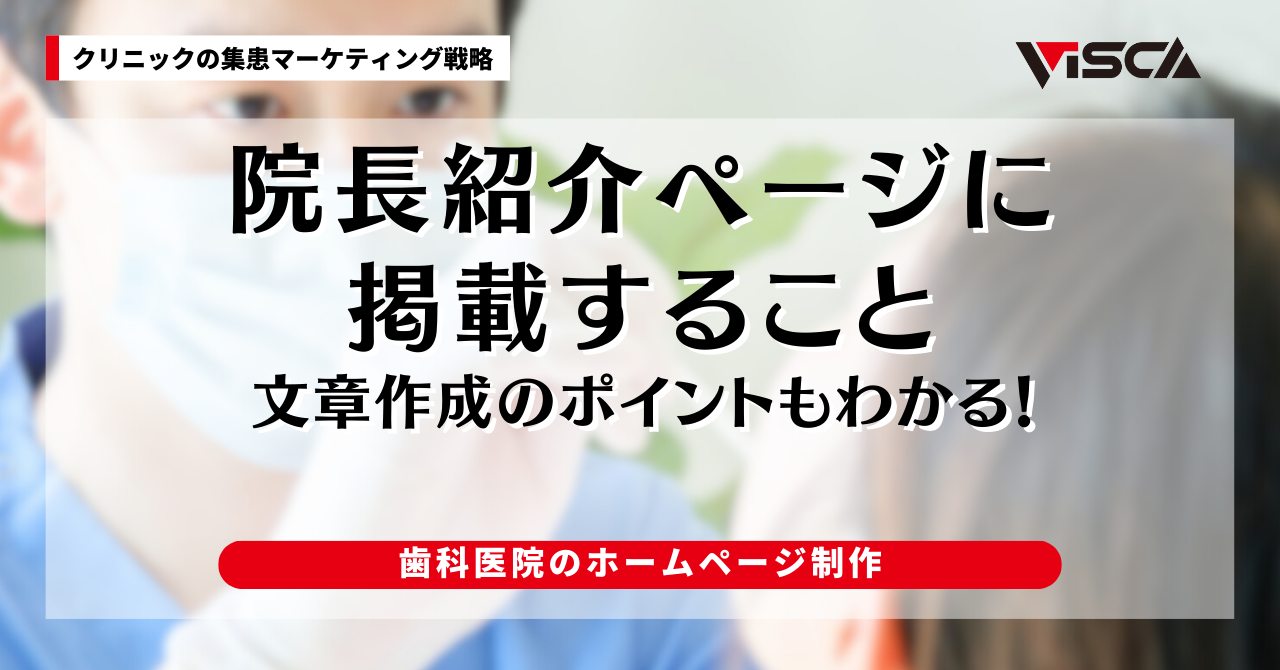




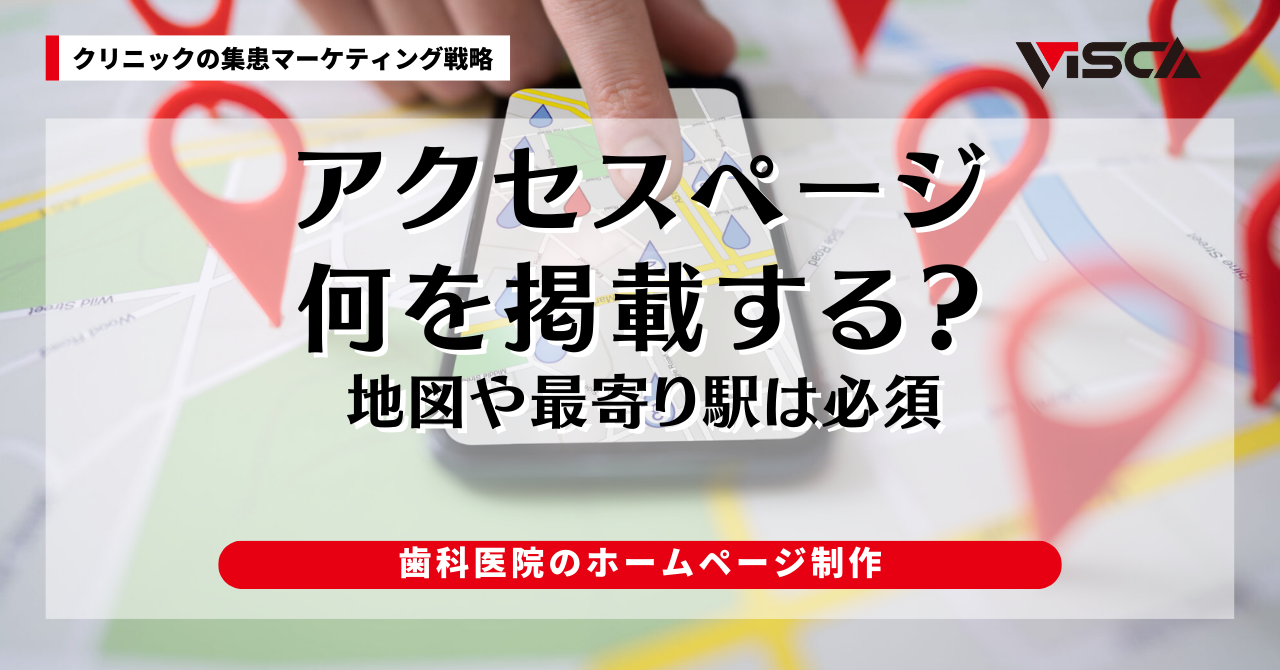


-22.png)


