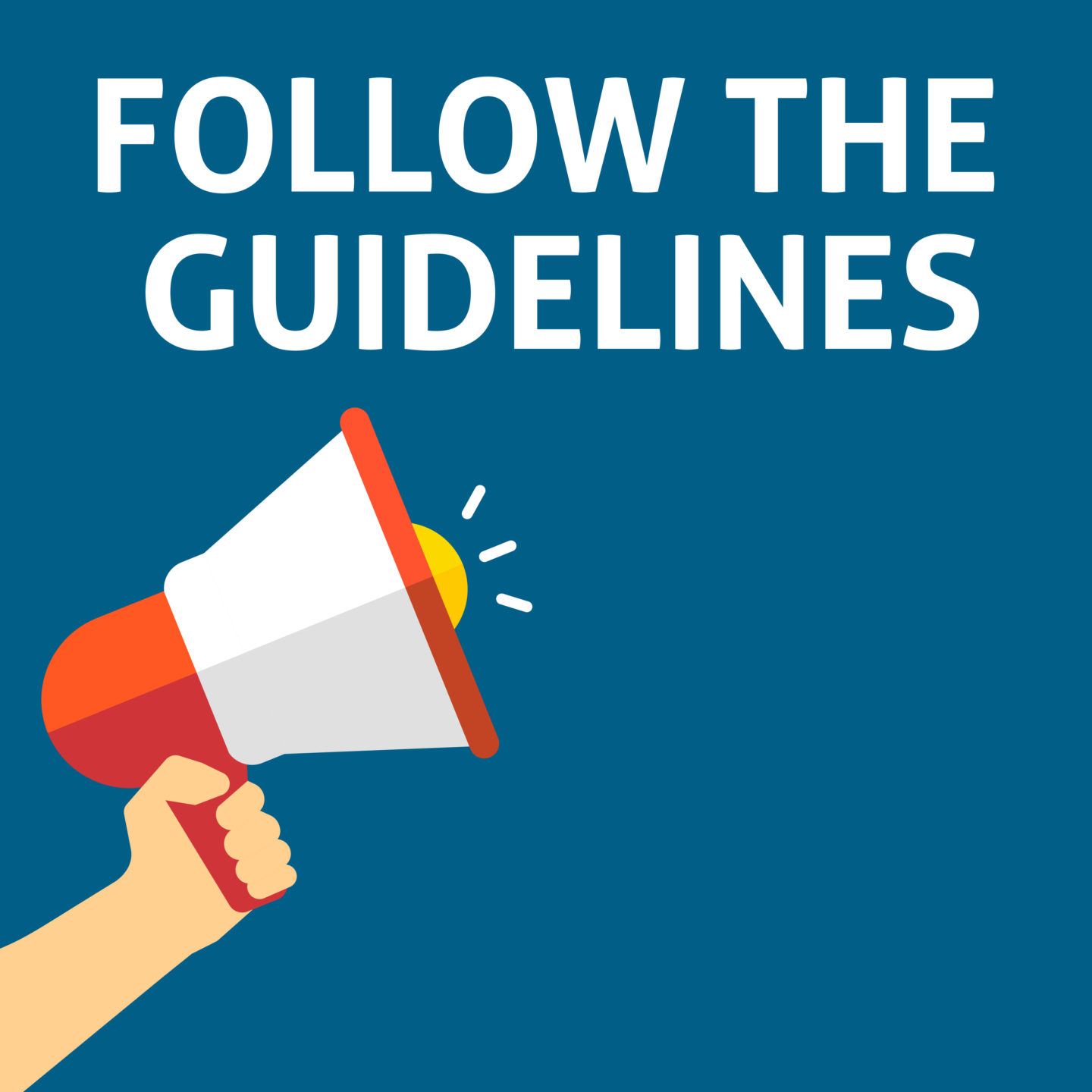※この記事は2023年12月に情報を更新しています。
医療広告ガイドラインとは
すべての医療機関のホームページには、厚生労働省によってガイドラインが定められていることをご存知でしょうか?
医療行為は人の健康や命に関わります。そのため、医療機関の「広告」には、記載していい内容が「医療法」によって厳しく定められています。
昨今、インターネット上の医療広告や医療サービスに関する消費者トラブルが増加していることから、医療機関のホームページも規制の対象とする「医療広告ガイドライン」が2018年6月に施行されました。
医療機関として、ホームページにおいても信頼性の高い情報を提供することが求められています。
2018年6月【医療広告ガイドライン】施行
- 医療法上の広告規制(折り込み広告、CM、看板、 ホームページ等)
- 虚偽禁止 (罰則あり)
- 誇大広告の禁止
- 基準違反への 中止・是正命令 (命令を無視した場合には罰則あり)
- 広告等可能事項を限定 (限定解除要件あり)
参考:
医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書 (第3版)(令和5年10月作成)
ガイドラインに違反したら
厚労省の委託業者によるネットパトロール、一般ユーザーの通報などによって「違反の疑いあり」と審査されると、委託業者から医療機関に通知がきます。この時点で、すみやかに修正対応することを心がけましょう。
通知から約1ヶ月後に、違反した点が実際に改善できているか確認されます。
1ヶ月間経過しても修正が行われない場合や改善が認められない場合は、自治体に情報提供が行われます。
違反内容が悪質な場合など、医院の閉鎖処分や6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科される可能性もあります。
WEB業界の対応
医療機関のホームページの監視体制が強化されるようになり、WEB業界でも「医療広告ガイドライン」に準拠したホームページ制作がなされるようになってきました。
しかし、医療広告に慣れていないWEB制作会社では、「医療広告ガイドライン」の正しい理解ができておらず、違反の文言を使用してしまったり、反対に過剰遵守してしまい、集患の妨げとなってしまう残念なケースもみられます。
そのため「医療広告ガイドライン」のルールにのっとり、適切な表現や修正を提案できるWEB制作会社に依頼することが重要です。
医療機関のホームページで避けるべき表現とは
医療機関のホームページに記載する際に、避けるべき表現について「虚偽」「著しい誇大」「薬機法などの法違反」の違反にわけてご紹介します。
虚偽
例1 加工・修正した術前術後の写真やイラストの掲載
あたかも効果があるかのように見せるために加工・修正した術前後の写真やイラストなど。誇大、または虚偽となります。
例2 「当院では、絶対安全な手術を提供しています」「どんなに難しい症例でも必ず成功します」
絶対に安全な手術を行うことは医学的に困難なため、虚偽となります。
例3 「一日で全ての治療が終了します」(治療後に定期的な処置が必要な場合)
症状や状況によって、すべての治療が必ずしも一日で終わらない場合もあり、誤解する可能性があるため、虚偽となります。
例4 「○%の満足度」(根拠や調査報告の提示はなし)
データの根拠を明らかにせずに、結果と考えられるもののみを示すことは「虚偽」として扱われます。また、調査対象が非常に限られていたり、謝礼を支払って誘導された調査結果も「虚偽」となります。
例5 「当院は、○○研究所を併設しています」(研究実態なし)
法第42条の規定に基づき、研究の実態がない場合は「虚偽」として取り扱われます。
著しい誇大1:他との比較などによって優良性を示そうとするもの
例1 「○○の治療では、日本有数の実績を有する病院です」「当院は県内一の医師数を誇ります」など
自らの医療機関が、他の医療機関よりも優良である旨を示す表現は誤認させやすいためNGです。
例2 「芸能プロダクションと提携しています」「著名人も○○医師を推薦しています」など
芸能人等が受診している旨の表現。事実であっても、他の医療機関よりも著しく優れているとの誤認させやすいためNGです。
例3 「他の医院より●●手術の成功率が高い」など
事実であっても、他の医療機関よりも著しく優れていると誤認させやすいためNGです。
著しい誇大2:医療機関にとって都合が良い情報の過度な強調
例1 「知事の許可を取得した病院です」
病院が都道府県知事の許可を得て開設するのは当然であるのに、特別な許可を得たかのように誤認させるおそれがあるため。
例2 「医師数○名(意図的に古い情報などを掲載)」
実態に即した人数に随時更新するよう努めるべきであること。
例3 「○○学会認定医」「○○協会認定施設」(活動実態のない団体による認定)
客観的かつ公正な一定の活動実績が確認されない団体、医療機関関係者自身が実質上運営している団体や活動実態のない団体などによる資格認定や施設認定が対象となります。
例4 「○○センター」(医療機関の名称または医療機関の名称と併記して掲載)
救命救急センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センターなど、一定の医療を担う医療機関である場合や、都道府県等が認める場合以外は、誇大となります。(病院内の掲示で「透析センター」などと掲示することはOKです)
例5 医療機関に都合のいい体験談
患者さんや医師・スタッフからの治療や診療についてのクチコミは規制の対象です。意図的に取捨選択したり、謝礼などによって誘導した感想の掲載も避けましょう。
著しい誇大3:早急な受診を過度にあおる表現、または費用の過度な強調
例1「ただいまキャンペーンを実施中」、「期間限定で○○療法を50%オフで提供しています」、「○○100,000円50,000円」、「○○治療し放題プラン」、「顔面の○○術 1か所○○円」
例2「無料相談をされた方に○○をプレゼント」
来院者や受診者全員にもれなくプレゼントするのであれば、総付景品という位置づけにはなりますが、医療と直接関連づけることは避けましょう。
著しい誇大4:不安を過度にあおり、不当に誘導するもの
例1 「○○の症状のある二人に一人が○○のリスクがあります」、「こんな症状が出ていれば命に関わりますので今すぐ受診ください」
特定の症状についてのリスクを強調し、医療機関への受診を誘導する表現。
例2 「○○手術は効果が高く、おすすめです」
特定の手術・処置などの有効性を強調して、その手術などを受けるように誘導する表現。
例3 「○○手術は効果が乏しく、リスクも高いので、新たに開発された○○手術をおすすめします」
特定の手術・処置などのリスクを強調して、それ以外の手術などへ誘導する表現。
「薬機法」「健康増進法」「不当景品類及び不当表示防止法」「不正競争防止法」の法違反
例1 「病気から回復して元気になる姿」をイメージさせるイラストや写真
回復を保証しているような印象を与えるため、“景品表示法”違反で行政処分の可能性があります。
ホームページを作る際に気をつけること
前述した通り「虚偽」「著しい誇大」「薬機法などの法違反」は掲載しないよう注意しましょう。
ホームページ上の文章はもとより、イラストや写真、データも、虚偽・著しい誇大・薬機法などの法違反にあたっていないかどうかの確認が必要です。
特に「ガンが治る」「若返る」などの文章・写真・イラストは、ガイドライン違反として行政処分の対象となる可能性があります。
ルールを守れば掲載できるもの
1.限定解除要件を満たせば、下記6つの専門医以外でも記載OK(歯科の場合)
・日本口腔外科学会 口腔外科専門医
・日本歯周病学会 歯周病専門医
・日本歯科麻酔学会 歯科麻酔専門医
・日本小児歯科学会 小児歯科専門医
・日本歯科放射線学会 歯科放射線専門医
・日本歯科専門医機構認定 補綴歯科専門医
※限定解除要件・・・ホームページに連絡先の明示・自由診療の内容・料金の明示・リスクの明示が必要。
(インプラントや矯正治療、ホワイトニングなどの自由診療は、治療の期間・回数、治療の流れも明示が必要)
※学会名・資格名は正式名称で記載が必要。
2. ビフォーアフターの写真はデータの明記があればOK
ビフォーアフターの写真を載せる場合は、「患者さんの年齢・症状・治療方法・治療期間・治療費・リスク・デメリット」などのデータを明記すれば、掲載が可能です。
ただし、撮影条件や被写体の状態を変えて撮影した術前術後の写真等を掲載することは、誤解を与える可能性があるため、規制の対象となる可能性があります。あたかも効果があるかのような印象を与えるイラストも避けましょう。
3. 診療や治療以外のクチコミはOK
医院へのアクセスがよい、スタッフが親切、院内に清潔感がある、WEB予約があるので便利、キッズスペースが充実しているなど、医療や治療と直接関係がないことはクチコミOKです。
ただし、患者さんや医師・スタッフからの治療や診療についてのクチコミは規制の対象となる可能性があります。
4.情報があれば、国内未承認の医薬品等の掲載もOK
「薬機法(旧薬事法)」では、承認前の医薬品・医療機器の名称、効能・効果、性能などについての広告が禁止されています。
しかし、歯科で扱う「インビザライン」「3mix法」「ドックベストセメント」などは、自由診療・費用・デメリット・治療回数・治療期間・治療の流れなどと、「入手経路」、「国内の同一医薬品の有無」、「諸外国における安全性の情報」を明示し、厚生労働省ホームページの「個人輸入において注意すべき医薬品等について」のページを情報提供すれば、掲載が可能です。
5.期間限定での料金の変更表記はOK
クリニックの会員限定ページや医院専用アプリ等で、キャンペーンや割引などの強調は品位を下げるためNGですが、期間限定で料金改定のお知らせをするのはOKです。
| 例)料金改定のお知らせ ●月●日~●月●日の間、「ホワイトニング」は料金を変更いたします。 オフィスホワイトニング/価格15000円(計2回) |
ホームページに掲載すべきこと
(自由診療を行う医療機関に限る)
1.治療の内容・費用・期間・回数等
自由診療は保険診療と異なり、医療機関によって治療内容や医療費が大きく変わります。
そのため「医療広告ガイドライン」では、通常必要とされる 治療内容・平均的な費用・治療期間・回数などを掲載し、情報をわかりやすく提供することが求められています。
平均的な費用が明確でない場合は、最低金額から最高金額までの範囲を示すなど、なるべくわかりやすく示すとされています。
2.治療等のリスク、副作用等
自由診療に関しては、リスクやデメリット、副作用などの情報に関しても、適切かつ十分な情報を提供することが重要です。
小さい文字で目立たないように記載したり、リンク先に掲載するのではなく、誰が見てもわかりやすく記載することが重要です。
日本ビスカでの今後の対応について
日本ビスカでは、「医療広告ガイドライン」を踏まえてホームページを制作しております。
ただし、規制についてはさまざまな解釈があり、自治体によって規制基準が異なる場合もあるため、大手企業も指摘を受けながら修正を繰り返している状況です。
万が一、弊社がホームページの保守をお引き受けしている医院様のもとに通知があった場合は、ビスカに修正依頼のご連絡をお願いいたします。
医院様のホームページが医療ガイドラインに即しているかをご確認されたい場合は、下記のフォームからお問い合わせいただけますと幸いです。
※今後の弊社の対応について詳しくは下記をご参照ください。
1.なるべく今のホームページの内容を残したいので、相談したい
(医院様のご希望をうかがいながら、医療広告ガイドラインをクリアできる表現を探るお手伝いをさせていただきます)
2.ガイドラインに準拠したものに修正したい
(医療広告ガイドラインに準拠して修正させていただきますが、自治体によっては修正通知を受ける可能性もありますので、あらかじめご了承ください)
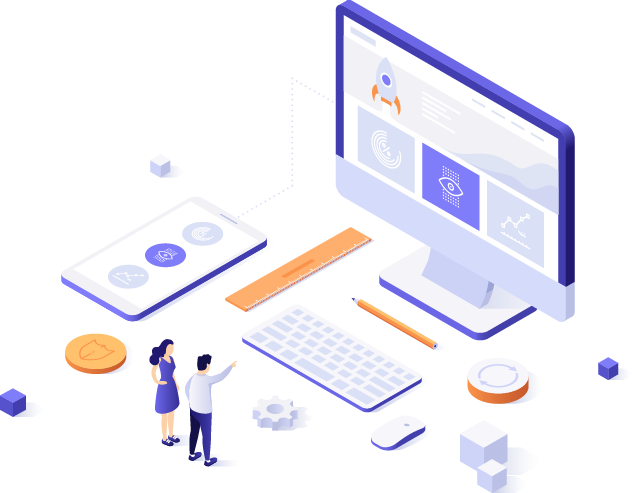
ホームページ制作サービス
ホームページは、クリニックの資産として育てていくことができるものです。まずホームページを開設することは、インターネットから集患するうえで欠かすことはできません。
ビスカでは、公開までのスケジュールやニーズ、ご予算に合わせて柔軟に対応できるホームページ制作プランを3つご用意しております。