2002年に厚生労働省が調査した「医療施設調査・病院報告の概要」では、ホームページの開設状況は病院53.7%、一般診療所12.9%、500床以上病院では91.0%という結果になっていましたが、3年後のホームページ開設状況は、病院70.2%、一般診療所20.5%と増加しています。
その後も、スマートフォンの普及率の上昇とともに、ホームページを持つ医院は増加傾向にあり、特に新規開院するクリニックにとって医院のサイトは開業のマストアイテムともいえる状況です。
もし、まだホームページを作っていらっしゃらない病院、歯科医院、動物病院の皆様は、ぜひホームページ制作を検討してみてください。
昔作ったサイトも、今風にリニューアルすることで、新たな集患につながります。
この記事では、ホームページ集患の成功事例や問題解決のための手法をご紹介します。
参考:
平成14年(2002)医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況
平成17(2005)医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況
事例(1):サイト分析に基づく効果的なコンテンツ配信で集患に成功
集患目的におけるホームページ運用が推奨されていますが、戦略を立てずにホームページ運用しても、思った効果は得られません。
ホームページ運用で集患に成功している医療機関は、まず自院やライバル医院のサイト分析を徹底的に行っています。
分析方法の一例
自サイトの訪問者数や閲覧が多いコンテンツをピックアップします。また、検索上位サイトのコンテンツ内容を確認しましょう。ライバルサイトと比べ、不足している情報があれば追加します。
次に、集患に成功しているエリアの住人の年齢層、最寄り駅の乗降数などをデータとして可視化することで戦略を立てます。
サイトの分析の際には、「Googleアナリティクス」や「Google Search Console」が役立ちます。
成功事例
ライバルサイトのコンテンツを分析した結果、医師の紹介ページが自サイトよりも充実していることがわかりました。
そこで、他の医院と差別化できる、院長の得意分野の診療ページを作り、医師の写真や症例や施術の写真を増やすことで、安心と信頼を訴求して集患に成功しました。
事例(2):予約の導線を用意して集患に成功
予約の導線を増やすことで、集患に成功した事例もあります。
ホームページをみて「この医院がよさそう」と思っても、そこから実際の来院アクションが起こらなければ、当然ながら集患にはつながりません。
ホームページを見ている時間帯は、夜間や就寝前、起床後などの時間帯が多いというデータがあります。そのため、そのタイミングで予約の電話をかけようと思っても診療時間外、というケースが多く発生します。
また、若年層の中には、電話をかけることが苦手と感じる人の割合も少なくありません。一方で日中は、お仕事や家事・育児で忙しく過ごす中で、忘れずに電話をかけなくちゃいけないという行為そのものが負担や負荷になってしまうことも。そのため24時間いつでも、短時間で手軽に予約が取れる体制が求められています。
問題を解決するには
このような背景から、病院や歯科医院の予約は、電話受付だけではなく、WEBやLINEを活用したものが増加しています。(矢野経済研究所の新規開業クリニックに関する法人アンケート調査結果では、予約システムの導入率は62%)
電話受付以外の手段を設け、「予約を取りたいと思った時に予約がとれる体制」を作りましょう。
成功させるための手法
WEBでの予約システムはもちろんですが、ホームページやLINEに専用フォームを設置して予約希望日時を送信してもらう、という方法でも、患者さんの予約~来院機会を逃さない手段として有効です。
いずれの場合でも、ホームページ上の目立つ位置にWEB予約ボタンを固定表示させることが重要です。
患者さんがホームページをみて「この医院に行こう」「予約しよう」と思ったら、すぐに目につく操作しやすい位置に「予約ボタン」があることで、高い意向をキープしたまま予約に誘導することができます。これが、ホームページからの集患効果=来院確度を上げることにつながります。
事例(3):動画を活用して集患に成功
動画を使った案内で、集患を成功させた事例もあります。
YouTubeやInstagramなど、動画が閲覧できるサイトが幅広い世代に浸透してきました。
これらのデジタルチャネルを活用して、集患に成功している医療機関が増えており、特に注目を集めているのがYouTube動画です。
制作したホームページにYouTube動画を埋め込むと、サイトの情報が充実するため、Googleからのサイトの評価を上げることもできます。
動画の有用性について
動画の有効性は、その情報伝達スピードの速さです。文字と比べて静止画(画像)は7倍、動画は5000倍の情報を伝えることができると言われています。
そのため、動画であれば、文字や静止画だけではわかりづらい院長先生・スタッフさんの雰囲気や院内の様子などを、見たままのリアルな情報として、わかりやすくスピーディに伝えることができます。
また、こうした動画をホームページに埋め込むことで、視覚的に高いアピール力が生まれます。動くものを思わず見てしまうという人間心理も作用し、ホームページの見た目にインパクトを持たせることが大切です。
成功させるための手法
医院ホームページで活用できる動画の主な種類としては
- 院長メッセージムービー
- 診療イメージムービー
- 院内紹介ムービー
- アクセスムービー
などが挙げられます。それぞれの動画に目的と役割がありますので、ホームページ上で特にアピールしたいポイントにあわせた動画の撮影制作が大切です。
こうした動画は、医院の良さを多方面から伝え、初めて来院する患者さんの不安感を取り除いたり、身近に感じてもらうことができるため、集患効果は大きくアップします。
まとめ
スマートフォンの普及率が高い今、病院の所在地や診療時間、休診日を調べる時も、電話よりインターネット検索に頼るケースが増加傾向にあります。
集患を成功させるのために、ホームページを開設するメリットは以下の通りです。
- 患者さんが求める情報をホームページに掲載できる
- 問い合わせの電話の手間を減らすことができる
- 休診日や診療時間外でも絶えず情報を発信できる
幅広い年代でインターネットを使用できる令和の時代では、集患のチャンスが24時間あります。
集患のチャンスを逃さないように、開院やリニューアルの際にはホームページを開設しましょう。
日本ビスカではホームページの制作から運用、予約システムとの紐づけ、動画撮影・制作など、幅広いサービスを行っています。
現在お持ちのホームページにおいて、集患効果を感じていないという方も、まずはご相談ください。
日本ビスカについて
日本ビスカは1980年代から、資材の提供やホームページ制作など、医療機関に向けて時代に合わせたサービスを行っている会社です。
病院や歯科医院、動物病院など、医療機関の集患でお悩みの方は、WEBマーケティングサービスのご利用もご検討ください。
WEBマーケティングサービス – 日本ビスカ株式会社 |医療機関専門のホームページ制作会社
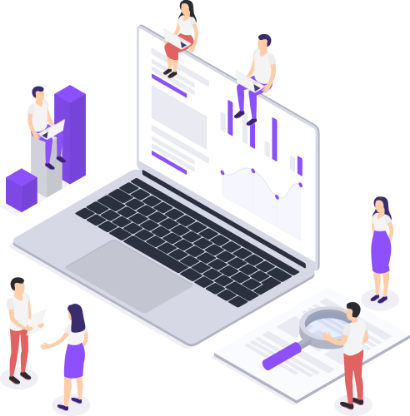
ホームページ保守・運用
ビスカのホームページ保守・運用サポートは、先生からのお悩みに最大限応え、保守料金以内で柔軟に対応しております。SEOやMEO対策に必要なGoogleマイビジネスなどの登録も行っております。まずはご相談ください。

-11-640x335.jpg)
-2-640x335.jpg)
-7-640x335.png)