「この広告表現は大丈夫?」
「どこまでならOKなのか、はっきり知りたい」
医療機関のWeb担当者・広報担当者の多くが一度は悩むのが、「医療広告ガイドライン」の正しい理解と運用です。
特に近年は、ホームページやSNS、ポータルサイトなどで医院をPRする機会が増え、意図せずガイドライン違反に該当してしまうケースも少なくありません。
そこで本記事では、医療広告ガイドラインを「わかりやすく」解説し、実務で注意すべきポイントを具体的にご紹介します。
医療広告ガイドラインとは?目的と基本ルール
まずはそもそも「医療広告ガイドライン」とは何なのか、そしてなぜそれが存在するのかを正しく理解しておくことが重要です。
ガイドラインは単なるルール集ではなく、患者と医療機関の信頼関係を守るための仕組みです。
この章では、ガイドラインの基本的な考え方と、医療広告が対象とする範囲についてわかりやすく解説します。
ガイドラインの目的は「患者を守ること」
医療広告ガイドラインとは、医療機関の広告が誇張・虚偽・誤認にならないように定められたルールです。
厚生労働省によって定められ、医療法第6条の5に基づいています。
広告を見て治療を選ぶ患者にとって、「本当に信頼できる情報なのか」「誤解を招かないか」を守ることが目的です。
広告とみなされる対象とは?
医療広告ガイドラインが適用されるのは、以下のような「広告」と認定される媒体や内容です。
| 対象媒体 | 主な例 |
| 印刷物 | チラシ、看板、パンフレット |
| Web媒体 | ホームページ、LP、SNS(自院アカウント) |
| 院外看板 | 電光掲示、ポスター |
※「患者が自発的に検索してたどり着く情報」は一部広告規制の対象外となる例もあります(限定解除要件あり)
医療広告でやってはいけないNG表現【7つの典型例】
ガイドラインの概要を理解したら、次に気になるのは「どこまでがNGか」ですよね。
ここでは、実際にクリニックのホームページや広告でありがちな、やってしまいがちだけどNGな表現を7つにまとめてご紹介します。
誤解やトラブルを防ぐためにも、ぜひ一つずつチェックしてみてください。
1. 最上級・No.1・最先端などの誇張表現
NG例:
- 「地域で一番人気!」
- 「最新の治療で必ず治ります!」
→ 根拠のない“最上級表現”は原則NGです。
仮に実績があっても、客観的データ(第三者評価)なしでは掲載不可とされます。
2. 効果を保証する言い回し
NG例:
- 「確実に治る」「100%白くなる」など
→ 医療行為には個人差があるため、「絶対」「確実」といった断定表現は禁忌です。
3. 体験談や口コミの掲載
NG例:
- 「患者さまの声」コーナーに感想を多数掲載
- ビフォーアフター写真をSNSで投稿
→ 体験談は原則NG。
限定解除要件(※後述)を満たせば一部掲載可能ですが、基本的には“広告とみなされる場所”では非推奨です。
4. ビフォーアフター画像の掲載
→ 治療効果を視覚的に保証してしまうため、原則NG。
どうしても使いたい場合は「限定解除要件(後述)」をすべて満たす必要があります。
5. 専門医・認定医の名称を誤って使う
→ 正式な学会認定がないにもかかわらず、「〇〇専門医」「〇〇認定医」と表記することは違反となります。
6. 治療内容に関する不十分な情報提供
→ 治療費・リスク・副作用などがきちんと明記されていない広告もNG対象となります。
7. 医療機関が管理するSNSの誤情報投稿
→ X(旧Twitter)やInstagramの投稿内容も、医療機関が発信するものはガイドライン対象になります。
限定解除要件とは?正しく情報発信するための鍵
実は医療広告ガイドラインにも、条件を満たせば「通常ならNGな表現」が認められるケースがあります。
それが“限定解除”という仕組みです。ここでは、この限定解除とは何か、どんな場合に適用されるのかを、わかりやすく解説していきます。
限定解除の3つの条件
| 条件 | 内容 |
| 自発的な検索行動による閲覧 | 患者が自主的にアクセスしている(広告誘導ではない) |
| 医院名など固有名称が必要 | 「〇〇歯科」などの明確な検索が前提 |
| 医療機関の管理下にある媒体 | 公式サイト・院内パンフなど(第三者運営サイトは対象外) |
これらを満たせば、体験談・ビフォーアフター・自由診療の詳細などの表現が可能になる場合もあります。なお、それぞれの症例について、主訴/診断名・患者さんの年齢/性別・治療期間・治療方法・治療費・治療のリスクなど、決められた情報をしっかりと掲載することが必要です。「自由診療の説明」や「写真使用」にはなお慎重な配慮が必要です。
医療広告ガイドラインの違反には罰則もある?
「少しくらいなら大丈夫だろう…」という油断が、思わぬトラブルにつながることもあります。実際にガイドライン違反が発覚した場合、行政指導や罰金などの措置がとられるケースもあるのです。
違反が発覚すると以下のような行政措置が行われる可能性があります。
- 是正指導・勧告
- 厚生局による調査・指導
- 悪質な場合は罰金(50万円以下)・広告停止命令
医療法違反として行政処分の対象となるケースもあるため、事前のチェック体制は不可欠です。
現場でできる、違反を防ぐためのチェック体制とは?
ガイドラインに準拠した広告運用を実現するには、「知っている」だけでは不十分です。重要なのは、日々の運用でミスや抜け漏れを防ぐ仕組みをつくることです。
院内チェック体制の構築ポイント:
- ホームページ・広告制作前に専門会社へ確認相談する
- 定期的に厚労省の最新ガイドラインや通知を確認する
- 制作担当・経営層・法務担当が一元管理できるフローを構築
特に広告制作を外注している場合、「制作会社任せ」にしないことが重要です。
最終責任は医療機関側にあるという認識が大切です。
まとめ|広告の自由とリスクの間で、正しい判断を
医療広告ガイドラインは、決して「広告を出すな」というものではありません。
伝え方と事実の示し方を工夫することで、信頼と集患の両立は十分に可能です。
正しい知識とパートナー選びが、医院の情報発信の質を左右します。広告表現とルールのバランスを理解し、伝えるべき情報を、信頼されるかたちで発信していきましょう。

リスティング広告
短期的にホームページのアクセス数を増やしたい場合には、確実に検索結果上位に表示されるリスティング広告がお勧めです。
ビスカではGoogle広告の有資格者が、集患に繋がりやすい効率的な運用を行っております。
日本ビスカ株式会社について
日本ビスカ株式会社 は、医療機関向けのWebマーケティング支援を専門に行っています。
- ホームページ制作:3,500医院超の制作実績。患者さんに選ばれるデザインと機能性を両立させたホームページ制作を行っています。
- SEO/MEO対策:地域密着型の施策で競争力を強化、エリアで選ばれるクリニックとしてブランディングを支援します。
- 広告運用:効率的なリスティング広告で費用対効果を最大化します。
資料請求・お問い合わせ
資料請求やお問い合わせは、こちらのフォームからどうぞ。専門スタッフが丁寧に対応いたします。
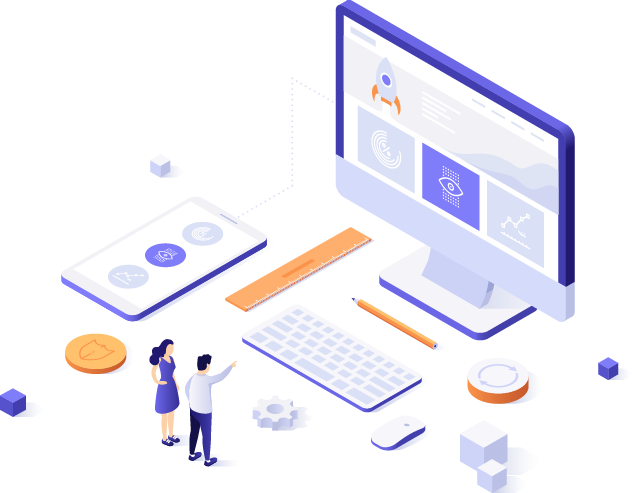
ホームページ制作サービス
ホームページは、クリニックの資産として育てていくことができるものです。まずホームページを開設することは、インターネットから集患するうえで欠かすことはできません。
ビスカでは、公開までのスケジュールやニーズ、ご予算に合わせて柔軟に対応できるホームページ制作プランを3つご用意しております。



